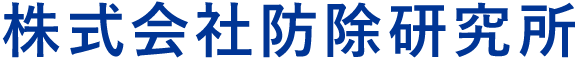当社について ABOUT
CONCEPT コンセプト
お客様を喜ばせるため
技術向上を怠らない
当社の理念は【常に喜ばれる会社を目指し、最高の笑顔と感謝の言葉をいただくため努力】することです。
そのために、お客様の気持ちを考え高品質なサービスを提供します。また、自分に厳しく「あと一歩」の精神を忘れず、日々努力を怠りません。そして常に技術向上を目指し、お客様に感動と安心を届けます。
FEATURE 当社の強み
01
検査と監視で
汚染源を持ち込まない
現在の衛生管理で主流なのが、薬品で衛生環境を維持する「部分管理」ではなく、施設の衛生管理を総合的に行う「IPM防除」です。管理者の方にも普段から施設を監視する意識を高めていただくよう協力しつつ、危険な状況を未然に防ぐため、当社は作業に取り組んでいます。
02
レスケミカルで
人体・環境にも優しい
当社では、いかに薬剤使用を最低限に抑えつつ害虫の生息値を低くするかを追求した【レスケミカル作業】を行っています。徹底した数値管理を行うことで効果が明確になるほか、薬剤特有の臭いを抑えます。また、準備や後片付けの手間も軽くすることが可能です。
03
各種認証・規格を
取得済み
当社は、2007年に国際規格ISO9001(品質マネジメントシステム)を取得し運用しています。さらに、2022年にはSDGs推進宣言を行い、2023年には当社はSBT認証を取得しました。当社は現在だけでなく、未来までも見据えてこれからも歩んでいきます。
STAFF 代表紹介
梅木 厚生 UMEKI ASTUO
- 役職
- 代表取締役
当社のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。害虫や害獣への対策は、人間が生活するさまざまな場所で欠かせないものです。当社は期待以上の高品質なサービスで、皆様に快適な空間をご提供します。まずは一度、ご連絡ください。
INFORMATION
会社概要
- 会社名
- 株式会社防除研究所
- 住所
- 【本社】
〒503-0833
岐阜県大垣市長沢町6-17
Tel:0120-51-7231
Fax:0584-71-8777
【中部営業所】
〒460-0007
愛知県名古屋市中区新栄2-15-13
Tel:052-269-1900
Fax:052-269-1901
【中部第二営業所】
〒504-0909
岐阜県各務原市那加信長町1-106
Tel:058-260-7703
Fax:058-260-7704
【関東営業所】
〒341-0025
埼玉県三郷市茂田井740-1
Tel:048-953-9520
Fax:048-953-9505
【北関東営業所】
〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1662-1-103
Tel:0283-85-9888
Fax:0283-85-9881
【関西営業所】
〒572-0077
大阪府寝屋川市点野5‐4‐48
Tel:072-813-9121
Fax:072-813-9969
【京滋営業所】
〒526-0037
滋賀県長浜市高田町7-13
Tel:0749-68-1570
Fax:0749-68-1581
【北陸営業所】
〒918-8013
福井県福井市春日1-5-11
Tel:0776-35-9001
Fax:0776-35-9019
【九州営業所】
〒818-0132
福岡県太宰府市国分1-13-32
Tel:092-408-8678
Fax:092-408-8739
- 営業時間
- 9:00~17:30
- 事業内容
- ネズミの対策
アライグマなど害獣の対策
ハチ・シロアリなど害虫の対策
各種殺菌消毒事業
衛生指導(HACCP)ISOコンサルティング
防除資材・薬剤販売